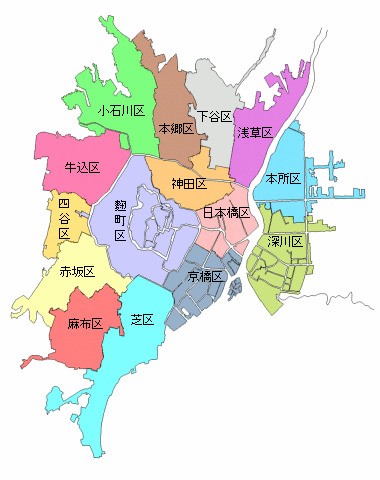日本における法学
私のもともとの専門は法学(刑法学)です。2018年度まで法科大学院で刑法を教えていました。
つまり、人類学者でも人口学者でも歴史学者でもないのですが、ある日ふと、「(日本では)法学者って意外とこの任務に向いてるんじゃないか?」と思いました。考えて、確信が持てたので、「エマニュエル・トッド入門講座」を始めることにしたのです。
「法律、それも刑法なんていう狭そうな領域の研究者がトッドの理論の解説に向いてるなんて、あるわけないだろう」と思った方のために、ちょっとご説明させていただきます。
明治時代、日本に初めて大学ができたとき、どんな学部があったかご存じですか。
明治10年に発足した東京大学が持っていたのは、法学部、文学部、理学部、医学部の4つでした。政治学部もないし、経済学部もない。社会科学にあたるものは、法学しかありません。
*政治学科は当初文学部の中にあり、帝国大学になるときに法学に移されたそうです。
ちなみに現在も日本に「政治学部」というのは存在せず(過去にはあったそうですが)、法学部の中にあるケースが多いです。現代のヨーロッパやアメリカでは、政治学は独立していたり人文社会科学や歴史と結びついているケースが多いようなので、法学との結合がスタンダードである日本は特殊なケースだと思います。
なぜか。いくつかの理由を思いつきますが、一番本質的な理由は、日本を西欧に伍する近代国家にするためには、何よりもまず、西欧と同じような(=近代的意味の)法制度そのものの構築が必要であったということだろうと思います。
*これが「急務」であったのは不平等条約改正のためですが、条約問題がなくてもその方向に進む以外に選択肢はなかったでしょう。
なお、「近代的意味の法」とか「近代法」とかいう言葉は、専門用語の一種です。近代に法律を作れば何でも「近代法」になるというわけではなく、「近代法」というためには、いろいろとうるさい条件があります。
*例えば、https://kotobank.jp/word/近代法-1160308 をご覧ください。
こうした条件を備えた法制度を持ち、それに基づいて国家が運営されているということが、欧米列強から信頼に値する国家と認められるためにどうしても必要だった。当時の日本にとって、新しい社会を作るということは、新しい法制度(に基づく国家)を作るということとほとんどイコールであったのです。
このような事情の下で、法学という学問は、明治以降の日本に、西欧的な「新しい常識」を導入するチャネルとして機能することになりました。西欧から思想や制度を輸入して、日本で受け入れ可能な形に整えて、社会に供給する。社会の要請の下で、日本を西欧式の国家に変えるための革命の綱領を作り続けたのが法学であった、といういい方もできるでしょう。
最近は廃れてきましたが、戦前・戦後の日本には、一般社会人を目指している(=法曹資格を取るつもりがなく、公務員を目指しているわけでもない)人が進んで法学部に入って勉強するという伝統がありました。それは、法学が、西欧に学んで新たな文明国家を築き上げるための「新しい常識」を供給する学問だったことの反映です。当時はみんなが「西欧式の新しい常識を身につけなければいけない」と思っていたのですね。
「新しい常識」(ないし革命の綱領)の根幹にあるのは、もちろん、近代主義=西欧中心思想です。つまり、法学は、エマニュエル・トッドの理論によって否定される運命にあるその思想の普及について、非常に大きな責任を担っているのです。
革命は成功しなかったー法学者は知っている
もう一つ、トッドへのコミットメントという点ではより本質的かもしれない事情があります。
法学は、明治以来、西欧的な常識に基づいた法制度の構築を助け、講義し、その運用を見守ってきました。行政の審議会やら民間の様々な会議に出席し、人々が従う制度が法の基本を踏み外さないように注視し、意見を述べてきました。
しかし、それによって、西欧的な法制度は日本に定着したのか、というと、してません。何度でも言いますが、「近代法」の一番肝心な部分(「法の支配」と言われるものです)は、日本に根づいていません。そして、そのことを一番よく知っているのは、法学者なのです(よく知らない法学者もいるとは思いますが、ちょっとおめでたい人だと思います)。
*「法の支配」が根付いていないとはどういうことか。一言でいいます。日本は法治国家(「法の支配する国家」の意味で使います)としては、行政の裁量権が強すぎるのです。「法の支配」の核心は統治機関(≒行政機関)を法のコントロールの下に置くことにあります。しかし、日本の場合、法は形ばかりは存在し行政の上に君臨しているようなフリをしているけれども(行政も法に従っているようなフリをしているけれども)、あらゆる領域で、重要事項の決定権を持っているのは行政です(ある行為を犯罪として処罰するかどうかを決める権限ですら、実際に行使しているのは検察官(=行政官)です)。
法律があろうがあるまいが行政が様々なことを差配し、国民がそれに従うというのは日本の人にとっては普通のことです。普通すぎて、「法の支配」とかその派生原理である「法律による行政」などを説明してもポカンとされてしまう。そのくらい普通だし、それこそが行政の責任だと思っている人も少なくない(行政官の中にもそういう人がたくさんいます)。このような社会のあり方は、しかし、もしも日本が西欧式の法治国家であるならば、明確に否定されなければならないはずのものなのです。
トッドは何度か日本を訪れていて、日本の研究者と対談や議論をしています。その記録を読んでいて、感じるのは、文学や歴史人口学の専門家の方たちが、トッドの理論の妥当性について疑念を持っている、あるいは確信を持てていないということです。この「迷い」は、おそらく、彼らに(例えば「トッド入門」を書くような)トッドの理論への全面的なコミットメントを躊躇わせる理由になっています。
彼らには、つぎのような逡巡があるようなのです。
「確かにトッドの理論にはなるほどと思うことが多い。しかし、家族システムにかかわらず、政治制度や法制度は、国家が法律を定め、制度を打ち立てることで、変えることができるはずである。そう考えなければ、明治以降(あるいは少なくとも第二次対戦後)の日本で、「近代的な」(西欧風の)政治制度、法制度が確立されたという事実を否定することになってしまうのではないか。」
例えば、速水融(歴史人口学)は、トッドとの対談で、次のような問いを発しています。
速水 ‥‥ 政治とか国家とか法制、これをどうお考えでしょうか。つまり、政治や国家や法制によって、家族構造あるいは農地制度というのは変わるものなのかどうか。というのは、日本を考えたときに‥‥明治になって日本が統一されてはじめて、明治政府が日本全体に適用される法律をつくろうとします。‥‥明治政府がまずやったことは、特に民法ですけれども、フランスからボワソナードという民法学者を呼んで、日本の民法を作ろうとしました。ところが民法典の案ができた時に、ドイツ法を学んだ穂積八束という日本の法学者が猛反対しました。つまりこれは日本の慣行に合わないと。そこで民法典論争という猛烈な論争が起こって、結局、ボワソナード派は負けてしまいます。そして日本的な民法、つまり長子単独相続を基本とする民法ができ、それが戦後までずっとつづきます。ところが戦後になって、今度は日本はアメリカに占領されて、そこでまた民法の改正があって、分割均分相続になります。
そのように法律がどんどん変わっていきます。こういうことは、たぶんフランスでは考えられないと思いますけれども、現実にわれわれ日本に生きている者としては、そういう中で変わっていくものだと考えざるをえない。民法だけでなくて、憲法からしていろいろ問題を含んでいますけれども、一体全体、政府や国、とくに法律はそういう社会の慣行を変える力を十分もっているとお考えかどうか伺いたいのです。
エマニュエル・トッド(石崎晴己 編)『世界像革命』(藤原書店、2001年)157-158頁)
ふふふ。
ご安心ください。
今から約20年前(2001年)、内閣に設置された司法制度改革審議会は、司法制度の改革に向けた意見書をまとめました。
*司法制度改革審議会「司法制度改革審議会意見書」(平成13年6月12日 司法制度改革審議会)https://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/report/ikensyo/index.html。(ロースクール制度の創設や裁判員裁判の導入などを意見したものです)
この意見書は、なんと(?)、つぎのような文章で始まっています。
民法典等の編さんから約100年、日本国憲法の制定から50余年が経った。当審議会は、‥‥近代の幕開け以来の苦闘に充ちた我が国の歴史を省察しつつ、司法制度改革の根本的な課題を、「法の精神、法の支配がこの国の血肉と化し、『この国のかたち』となるために、一体何をなさなければならないのか」、「日本国憲法のよって立つ個人の尊重(憲法第13条)と国民主権(同前文、第1条)が真の意味において実現されるために何が必要とされているのか」を明らかにすることにあると設定した。
これを読んで、驚く方もいるのではないでしょうか。何しろ、2001年の日本における根本的な課題が、「法の精神、法の支配を「この国のかたち」とすることであり、個人の尊重と国民主権を実現すること」なのです。「日本国憲法って何なんですか」と言いたくなりますね。
しかも、この「意見書」の中に、日本がいかに法の支配を欠き、個人の尊重、国民主義を実現できていないかを論証する文章はありません。つまり、この文章を読む関係者にとって、「法の精神、法の支配が日本に根づいていない」という認識は、争うまでもない、当然の前提として共有されているのです。
私の経験
私自身の経験もちょっとお話ししようと思います。
私は、中高生のころから、ただ社会に興味がありました。どの専門科目を選べばよいのかわからなかったので(今もわかりません)、何となく法学部に入りました。講義に出て直ちに「間違えた!」と悟り、あまり授業に出ない学生として4年間を過ごしました。
でも、学者にはなりたかった。なりたかったので、手近にあった刑法学の道に進みました。
真面目に取り組んでみたらこれが意外に面白く、資質としては向いていました。
よく覚えているのは、好き放題に本を読んで物を考えていた大学時代を終えて、大学院で法学の研究を始めたとき、「なんかラク」と感じたこと。
何ていうのでしょう。法学の中の概念って、みんなカッコがついているのです。まったく手ぶらで、ただ一人の思索がちの人間として、例えば自由という言葉を使うとすると、そんなものは本当にありうるのか、あるとしたら何なのか、そんなものを論じることに意味があるのか、‥‥と無限に疑問がついてまわってくるものですが、法学の中だと、ある程度専門用語として、「ここでいう自由はその自由ではなくて、あくまで「法学的な意味の」自由ですから~」という感じで、さくさくと議論を先に進めていける。しかも、その議論は、現に存在し機能している法制度をよりよく機能させるための議論なのですから、大前提として「意味はある」。
しかも、法学、なかでもとくに刑法学という学問は、根っこにある価値観が、リベラリズム、それも(詳しくは知りませんが)古典的リベラリズムといわれる、イギリス庶民(あるいはパンクロック)のような素朴な自由主義思想です。
自分の知的能力を駆使して、素朴な自由主義に基づく分析をすれば、評価され、世の中の役に立つ(らしい)。何と夢のようなことでしょうか。
そういうわけで、私は、非常に消極的な理由で選んだ刑法学の道を歩み続けることになりました。ずっと後になって「カッコがついている」ということの意味を思い知ることになるのですけど。
日本社会の現実を知る
私は刑法学者であると同時に医事法学者でもあります。医療や医学研究の領域では、様々な形で現場と関わる仕事をさせてもらいました。
研究機関の倫理委員会から、研究プロジェクトの法的・倫理的・社会的課題を検討するための委員会、厚生労働省や文部科学省の審議会にも多数参加しました。医療や医学研究に関連する学会などのシンポジウムなどに呼んでいただいて講演をしたり討議をすることもありました。
私に声をかけてくれる方というのは、基本的に、現在の法制度(というより、多くの場合は、インフォーマルな行政指導的規制)に満足しておらず、「なんかおかしいと思うんだけど本当のところどうなの?」「本当に自分たちが妥当だと思うことを正当に実施していくためにはどうしたらいいの?」と思っている方たちです。
そういう方達と一緒に、あるべき姿を考えていく仕事は本当に楽しかった。法学者から見ると、行政の規制のあり方や現場の常識などはツッコミどころ満載なので、「法学的にはここはすごくおかしくて、ほとんど憲法違反」「こうやれば問題ないはず」「ここについては公的な規制がない状況だから、自主的にガイドライン的なものをつくってやっていくのがよい」等々と指摘し、実際にルール案を一緒に考えたりもしました。
「おかしい」という法学者からの指摘は、医学系の研究者の方々にとっては、目から鱗というか「え、ほんと?」という驚きであったようでした。私たちの指摘や提案は、彼らには喜んで受け入れられ、とてもやりがいを持って仕事をすることができました。
しかし、10年以上もそんな仕事を続けると、頭でっかちな法学徒にも、日本の現実が見えてきます。
私たちがどれほど法理論上の誤りを指摘し、みんなを感心させても、現場の状況がまったく変化しないのはなぜなのか。
この間には私自身も少し偉くなり、行政の審議会などで、法案の内容に正面から意見を言える立場になっていました。しかし、ごく標準的な法学的立場に立って意見を述べて、その場にいるほとんどの人を納得させても、はたまた行政官と裏で何度も議論をし、憲法違反の疑いを払拭するために必要な措置を伝え、何度「わかりました」と言わせても、肝心なポイントが修正されることは決してない。いったいなぜなのか。
答えは一つしかありません。
日本の法制度は、日本の社会で通用していないということです。
日本社会は、法学の教科書(=社会科の教科書)に書いてあるのとは異なる、固有のシステムで成り立ち、動いている社会である。
もし、これが「近代化の遅れ」であるなら、改善の努力を続ければよいのですが、私一人の経験からも、そんな生やさしいものでないことは、明らかであるように思えました。その上、「民法典等の編さんから約120年、日本国憲法の制定から70余年」が経った2021年に、このシステムはビクともせず、見ようによっては、ますます強まっているように見えるのです。
さて、どうしたものか。
法学を離れる
法学者の中には「法が大好き」という人がいます。近代法の思想に強く惹かれ、それを法制度として機能させることに情熱を抱く人たちです。この人たちは、日本社会に、近代法が定着していないことを知っていると思いますが、「少しでもそれに近づけることが日本社会をよくする道だ」と信じて、活動を続けているのだと思います。
また、東大を出て、とくに優秀な東大教授として名を馳せるような人たちは、日本社会と法理論との齟齬をおそらく熟知していますが(意識化の程度は人によります)、その中でなんとか折り合いをつけることを自らの使命としている人たちといえます。
*他の分野から見ると胡散臭く思えるかもしれませんが、法学というのは成り立ちからして権威的な学問なので、法学向きの優秀な人材が東大に集まりがちであるのは事実だと思います
近代主義の理想との相違をことごとしく非難したりせず、職人的なバランス感覚で落とし所を探るのが彼らの職責です。
*なお、多分どの法分野でもそうだと思いますが、この「職人的なバランス感覚」をある程度は身につけないと、決して一流の法学者として認められることはありません。そうこうしているうちに、自分が何をしているのかよくわからなくなってしまっている人というのも、結構いるように思えますが。
私は、法に関心があったわけでも、エリート官僚的なメンタリティで日本社会を導くことに関心があったわけでもなく、単に「社会に興味がある」というだけで法学者になりました。近代法の理想(リベラリズムですね)は、自由を求める若い者には何しろ魅力的なものなので、私もしばらくの間は幻惑され、「法が大好き」という人たちと同じように、「日本社会を少しでもそれに近づけること」に対して、情熱をもって取り組むことができました。
しかし、「教科書に書いてあることって、全部フィクションだったのか」と、おなかの底からしみじみと理解してしまったとき、それでも同じ活動を続けるのは、私には無理でした。
私は不可能なことのために活動することができない人間なのです。ご存知のように、なかには道徳的な感情、価値あるいは善なるものを提唱するだけで満足し、それが実現できるかどうかについては関心をもたない人々がいますが、私はそうではありません。絶望の歌が最も美しい歌であるとは思わないのです。虚空に向かって叫ぶこと、自己満足のためにいくつかの価値を提唱することには、関心がありません。
エマニュエル・トッド(石崎晴己 編)「世界像革命」(藤原書店、2001年)120頁
この状況で、社会科学者である自分のやるべきことは、現実をフィクションに近づけようとすることではなく、現実をよりよく知り、伝えていくことであるように思えました。何より、高校生の自分は、まさに「それ」を知りたかったのですから。
しかし、それはもう刑法学の仕事ではありません。法学とも言えないでしょう。仕方なく、私は仕事を辞めて、現在に至ります。
奇跡に見舞われる
では、法学部に入り、刑法学者になったことを後悔しているかというと、それは全くしていません。
大学を辞めて、歴史とか、経済とか、いくつかの気になる分野を勉強し、同時に、改めて、トッドの理論に取り組みました。そのとき感じた気持ちを、どう表現したらよいのか。
昔、福田恒存が小林秀雄の文章について、「(この文章を)これほど味わうことができるのは自分だけではないかと、これは自惚れとはまったく異なる、深い幸福感のようなものを堪能した」という趣旨のことを書いているのを読んだことがあります。池田晶子さんも小林秀雄について同じようなことを書いていたかもしれない(福田恒存のその文章も引用していたかもしれない)。
*福田恒存も小林秀雄も池田晶子もご存じである必要はありません。
「こんなことを言えるなんて、すごいな~」と思っていましたが、いま、私がトッドの理論について感じるのはまさにこれです。
社会に関心を持ちつつ、なりゆきで実定法学者になり、西欧近代の物差しを現代日本にきっちり当てはめてみた。ああすればいい、こうすればいいと言ってやってみても、その目盛り一つがどうしても動かない。その過程で得た認識、経験した感情のすべてが、現在、私がトッドの理論に全幅の信頼を置き、理解し、味わい尽くす下地になっているのです。
おかげで、現在の私は、高校生のときに知りたかったことをすべて知り、その先を考えることができるようになっています。なんてありがたいことでしょうか。奇跡です、奇跡。いや、本当に。大して興味もないのによく法学を選び、研究者にまでなったと、自分を褒めたい気持ちでいっぱいです。
他の領域で研究をしていたとしたら、おそらく、文理を問わず、社会に一定の関心がある真面目で良心的な人々のほとんど全てが抱いているリベラリズムの夢ないし幻想を完全に捨て切ることはできなかったでしょう。
ちょっとおかしいと思いつつ、「合理的な」提案をし、変える努力をして、変わらないと嘆くことを繰り返す。そんな知識人であり続けたと思います。
いま、そこら辺から外に出て、次に進むことがとても大事だと思うので、準備ができている人たちと一緒に、それをしようと思います。
その第一弾が、エマニュエル・トッド入門講座です。