脱キリスト教の開始とイデオロギーの誕生
宗教も国王も打ち捨てたフランスは、その「権威」の穴を何で埋めたのか。結論から言おう。学問である。
宗教の死によってイデオロギーの誕生が可能になる。人間は、消え失せた神のイメージの代わりに、直ちに新しい理想社会のイメージに飛びつく。1789年以降、ヨーロッパは相次いで押し寄せるイデオロギーの波に洗われることになる。フランス大革命、自由主義、社会民主主義、共産主義、ファシズム、民族社会主義……これらのイデオロギーの波は、時間と空間の中での脱キリスト教化の各段階に結びついている。
『新ヨーロッパ大全 I 』249頁
ヨーロッパにおける脱キリスト教化の開始時期とイデオロギー誕生の時期は一致している。
1789年〔フランス大革命〕以来、かくも多くの政党と共和国を育むことになった自由・平等のイデオロギーは、脱キリスト教化のわずか数十年後に発生している。脱キリスト教化は、1730年から1750年の間に、フランスの国土の三分の二で起こったのであった。
『デモクラシー以後』52頁
文字を読むようになった人々は信仰を捨て、唯一の正統教義のかわりに、好みのイデオロギーを選んで熱狂的に支持する。民主主義の始まりである。
波を生み出すのは識字化した市井の人々だが、イデオロギーそのものを生み出すのは学問の府、大学である。ロック、ルソー、カント、ヘーゲル、マルクス。彼らはみな何らかの形で大学やアカデミーに関わりその思想を世間に流布していった人々であり、学問が宗教に代わる権威となった時代を象徴する人々といえる。
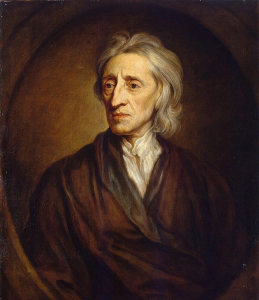
中世に神学者を輩出してキリスト教の権威を支えた大学は、脱宗教化の後には、自らが権威の源泉となって、近代国家を支えたのである。
脱キリスト教の完成とイデオロギーの崩壊
しかし、市民がイデオロギーに熱狂する時代は長くは続かなかった。
1965年から1990年までの間、ヨーロッパのイデオロギー・システムの大部分は、容赦ない解体のメカニズムに曝される。それは信条を破壊し、政党を弱体化し、政治的選択というものの本性を一変させ、全ては虚しく意味が無くなったという感情をいたるところで醸し出すのである。
『新ヨーロッパ大全 II 』265頁
フランス共産党は1978年には20.6%の票を獲得していたが1988年には11.3%に落ち込む。同様の低落傾向は明確なイデオロギーを有するすべての政党に認められ、共産党、ドゴール主義(民族主義右翼)、穏健右派、キリスト教民主主義の4政党の合計得票率は1962-1988の間に79.2%から49%へと大幅に低下するのである(なお、この間に行き場を失った票の受け皿として勢力を拡大したのが社会党である)1『新ヨーロッパ大全 II』314-318頁。
1965年-1990年というこの時期、イデオロギーの崩壊という現象は、主義主張の中身を問わず、あらゆる政治的信条を平等に呑み込んでいく。この動きは、フランス、イギリス、オランダ、デンマーク、スペイン2いずれも核家族が中心であるといった国々でとりわけ大きくかつ急速だった。
何がこの変化をもたらしたのか。答えは単純である。
この変化の発端は実に平凡で、それは宗教の危機、ヨーロッパ圏の歴史上最後の宗教危機で始まった。
『新ヨーロッパ大全 II 』265頁
フランスでは、中心部の脱宗教化は1730-1800年に完了していたが、周縁部に残っていた宗教実践が1950-1970年の間に失われた。ヨーロッパ全体では、最後まで生き残っていた反動的カトリシズムが1965年から1990年にかけて消滅していく。
イデオロギーの時代は、脱キリスト教化の開始とともに訪れた。ところが、脱キリスト教化が完了すると、同時にイデオロギーの方も力を失ってしまうのである。
フランスの国土の三分の一に活動的な宗教が存続したことは、フランスのイデオロギー・システムの良好な作動のために最後まで必要であり続けた、ということが分かる。共和主義、社会主義、共産主義は、実際上は、残存的カトリック教との対抗関係の中で自己定義を行なったのであり、残存的カトリック教は、いわば陰画(ネガ)の形で、それらのイデオロギーを構造化したのである。この宗教の死は、まるでそれが跳ね返ったかのようにして、近代イデオロギーを死に至らしめた。
『デモクラシー以後』52-53頁
宗教的危機のインパクトー西欧の場合
この連載の開始時に書いたように、トッドは現代の西欧世界の危機の根源には宗教的危機があるという立場を取っている。
神なき世界の出現は、幸福感につながるどころか、激しい不安、欠落感へと立ち至る。‥‥
天国、地獄、煉獄の消滅は、奇妙なことに、すべての地上の楽園の価値を失墜させてしまうのだ。‥‥ すると意味というものの必死の探求が始まる。それは通常、歴史的には、宗教が統制していた金銭、性行動、暴力という項目に括られる領域における極端な感覚の追求という形で行われるのである。
『デモクラシー以後』54頁、55頁
ここから、トッドは、人間精神の安定にとって信仰が古来から果たしてきた役割の決定的重要性という命題を引き出すのだが、私の考えは少し違う。
確かに、ヨーロッパの人間の精神の安定にとってキリスト教が果たしてきた役割は決定的に重要であったと思う。
なぜかといえば、キリスト教は、ヨーロッパの主要な家族システムである核家族に欠けている「権威」を補う役目を担っていたからである。
国家というシステムは、多数の人間が一定の領域内で共存していくためのシステムであり、安寧秩序の維持のためには、人々が共通の「正しさ」の存在を受け容れることが不可欠である。
共通の「正しさ」は、ルールの基盤となって人々の行動を制御することを可能にし、それ以上に、共通の「正しさ」の下にあるという感覚によって、人々の心を繋ぎ、安定させる。
この共通の「正しさ」を基礎付けるものが「権威」であり、だからこそ、権威の誕生(=直系家族の誕生)が国家の誕生と同期するのである。
直系家族の民や共同体家族の民が自然に持っている「みんなの正しさ」の感覚を、核家族の民は持っていない(家族システムと価値の対応関係についてはこちら)。
そこで、彼らは、彼岸にいる唯一絶対の神の存在を信じることによって、共有物としての「正しさ」を希求するという心の型を手に入れた。
核家族の国家は、神を畏れ、神への接近を希求するという心の動きが共有されたことで初めて、その統合を保つことができたのである。
西欧近代が見せた学問への情熱やイデオロギー的熱狂は、おそらく、神を希求する心の型がそのまま世俗の事物に転用されたことで可能になったものである。
だからこそ、それは信仰の喪失とともに失われ、西欧に深刻な精神的危機をひき起こすことになったのだ。
学問の時代の終わり
識字化の進展とともに、神の存在に疑念を抱くようになった人々は、その不安を癒すべく、頻りに神の存在について論じた(17世紀前半~)。デカルト(1596-1650)が神の存在証明を試み、パスカル(1623-1662)は神の実在に賭け、スピノザ(1632-1677)は汎神論を説いたように。
17世紀後半になると、核家族のヨーロッパ(イギリス、フランス)は、神の教えの代わりに人間理性を讃えるようになり、啓蒙の時代、言い換えれば、科学とイデオロギーの時代がやってくる。
アカデミアに属する知識人がヒーローとして燦然と輝いた時代。ジョン・ロック(1632-1704)を端緒、ミシェル・フーコー(1926-1984)を掉尾とするなら、こうした時代は約300年間続いたことになる。

人文・社会科学の研究者で、この時代のヨーロッパの輝きに憧れたことがない人は少ないだろう。なぜ日本からは世界を魅了する力強い思想が生まれないのかと嘆き、強い「個」の確立を説く声はつい最近までよく聞かれた。同様に、社会における大学および学問の地位の高さにおいても、ヨーロッパは日本の大学人の憧憬の的であったように思う。
西欧における学術・イデオロギーの繚乱は、全知全能、唯一絶対の神のいました台座に渦巻く磁場が可能にしたものであり、キリスト教のドーピング作用が失われゆく過程のヨーロッパに一時的に顕現した特殊な現象であったと考えられる。
ご先祖さまに守られ「おてんとさま」3直系家族の権威の性質を一番よく表しているのは「おてんとさまが見ている」という感覚や「おまわりさん」への親しみの感覚だと思う。詳細は(もしかしたら)後日に照らされてぬくぬくと国家を営む日本にそのような磁場が渦巻く場所はない。補う必要がないから補填物が生まれなかったという事実を、「遅れている」とか「劣っている」と評価するのは端的に誤りだし、ばかげてもいるだろう。
いずれにせよ、キリスト教の残火が輝いた時代は終わった。それは20世紀末できっちり終了し、私たちはすでに西欧の特別な輝きが失われた世界を生きている。長くその輝きに幻惑され、恩恵も受けてきた私たちは、その現実の意味するところをよくよくかみしめる必要があると思う。
今日のまとめ
- ヨーロッパでは脱宗教化の開始とともに学問・イデオロギーの時代が始まった
- 脱宗教化が完了すると同時に学問・イデオロギーの時代も終了した
- 西欧近代における学問・イデオロギーの特別な輝きは「唯一絶対の神を希求する」心の型が世俗の事物に転用された結果である
- 西欧の宗教的危機が特別なインパクトを持ったのは、キリスト教が核家族に欠けている「権威」を代替していたからである
- 1『新ヨーロッパ大全 II』314-318頁
- 2いずれも核家族が中心である
- 3直系家族の権威の性質を一番よく表しているのは「おてんとさまが見ている」という感覚や「おまわりさん」への親しみの感覚だと思う。詳細は(もしかしたら)後日

